森の奥深くに、古い言い伝えのある泉があった。
その泉は、落とした斧を金や銀に変えて返してくれる不思議な力を持つと言われていた。正直者には金の斧を、嘘つきには何も与えない——そんな道徳的な教訓を含んだ話として、村人たちの間で語り継がれてきた。
しかし、その日、泉に落ちたのは斧ではなかった。
研究者の男は、民俗学の調査でこの森を訪れていた。足を滑らせ、気がついたときには冷たい水の中にいた。慌てて水面に顔を出そうとしたその時、泉の底から光が立ち上った。
「おや、珍しいものが落ちてきましたね」
声の主は、昔話で語られる通りの老人だった。白いひげ、慈愛に満ちた表情。しかし、その目の奥には測りがたい深淵があった。
「あなたが落としたのは、この黄金の人間ですか?」
老人が差し出したのは、確かに男と同じ顔をした人物だった。しかし、その肌は金色に輝き、表情には生気というものが感じられない。まるで精巧な人形のようだった。
「それとも、この白銀の人間でしょうか?」
今度現れたのは、銀色に輝く男だった。やはり美しいが、どこか冷たく、人間らしい温もりに欠けていた。
男は混乱した。これは夢なのか、それとも現実なのか。自分が落としたのは自分自身なのだから、正直に答えるべきなのは分かっている。しかし、その答えが何を意味するのか、彼には理解できなかった。
「いえ、私が落としたのは、普通の人間です。私自身です」
老人は満足そうに頷いた。
「正直者ですね。では、お礼に三体とも差し上げましょう」
その瞬間、男の意識は途切れた。
目を覚ましたとき、男は泉のほとりに横たわっていた。夕日が森を赤く染めている。濡れた服が肌に貼りついて不快だったが、それは確かに現実の感覚だった。
「夢だったのか……」
そう呟きながら立ち上がろうとしたとき、彼は気づいた。自分の隣に、もう一人の自分が倒れていることに。
金色の肌を持つ自分が、静かに横たわっている。息をしているのかどうかも分からない。触れてみると、金属のように冷たく、しかし確かに人間の体温のような温もりもあった。
さらにその向こうには、銀色の自分もいた。
男は震えた。これは夢の続きなのか、それとも現実なのか。自分の手を見つめる。確かに普通の肌の色をしている。普通の人間の手だ。
しかし、ふと疑問が浮かんだ。自分が「普通の人間」だと、なぜ確信できるのだろうか。
記憶を辿ってみる。研究室での日々、同僚たちとの会話、恋人との時間——すべて鮮明に思い出せる。しかし、それらの記憶が本物だという保証はどこにあるのだろうか。
金色の自分も、銀色の自分も、同じ記憶を持っているのではないだろうか。
男は金色の自分の顔を覗き込んだ。完璧に同じ顔立ちだった。しかし、その表情には何かが欠けていた。苦悩、迷い、希望——人間らしい複雑さが感じられない。
銀色の自分も同様だった。美しいが、どこか空虚だった。
「私が本物だ」
男はそう呟いた。しかし、その言葉に確信を込めることができなかった。
もしかすると、本当の男はすでに泉の底に沈んでいて、今の自分こそが複製なのかもしれない。あるいは、三体すべてが複製で、本物はもうこの世にいないのかもしれない。
夜が更けていく。男は金色と銀色の自分を見つめ続けた。彼らもまた、いつか目を覚ますのだろうか。そして目を覚ましたとき、自分のことを「本物」だと思うのだろうか。
翌朝、村人たちが男を発見したとき、彼は一人だった。金色と銀色の人間は消えていた。夢だったのか、それとも朝露に溶けてしまったのか。
男は何も語らなかった。いや、語ることができなかった。
彼は研究を続け、論文を発表し、恋人と結婚した。普通の人生を送った。しかし、時折、鏡を見るたびに疑問が頭をもたげる。
この顔は本物なのか。この記憶は本物なのか。この人生は本物なのか。
そして何より、この疑問を抱いている自分自身は、本物なのか。
泉は今も森の奥で静かに水をたたえている。時々、金色や銀色の人影が水面に映ることがあると、村人たちは噂している。
しかし、それが本当のことなのか、それとも単なる光の加減なのか、誰にも分からない。
分からないということだけが、確かなのかもしれない。
男が老いて死を迎えるとき、彼は最後にもう一度、あの泉のことを思い出した。
もしかすると、死ぬのは自分だけで、金色と銀色の自分は永遠に生き続けるのかもしれない。あるいは、自分の死と共に、すべての複製も消えてしまうのかもしれない。
それとも、死んだ後に、本当の自分が別の場所で目を覚ますのかもしれない。
最期の息を引き取るとき、男の脳裏に浮かんだのは、あの老人の言葉だった。
「お礼に三体とも差し上げましょう」
三体とも、と老人は言った。
では、あのとき泉に落ちた男は、一体どうなったのだろうか。
その答えを知る者は、もはや誰もいない。
ただ、森の奥の泉だけが、すべてを知りながら、静かに水をたたえている。
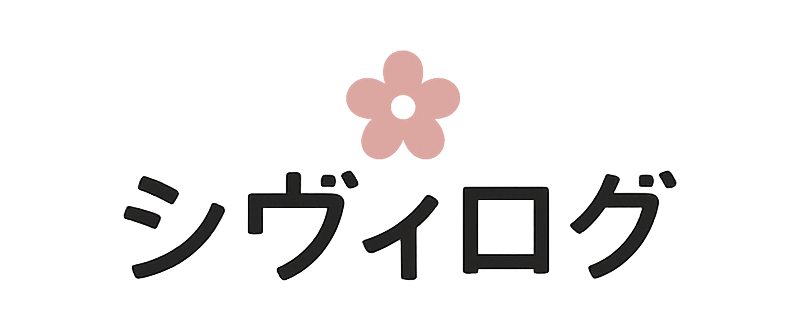



コメント