日本に住んでいると当たり前のように使っている日本語。しかし、世界に目を向けると「日本語は世界で最も習得が難しい言語の一つだ」と言われることがあります。
日本語を母国語として話している私たちからすると、一体何がそんなに難しいのだろう?と疑問に感じるかもしれません。しかし、外国人の視点に立つと、日本語には多くの「壁」が存在していることがわかります。
今回は、長年日本語に触れてきた日本人である私が、あらためて日本語の奥深さと、それが外国人にとってなぜ難しいのかを、英語との比較を交えながら掘り下げていきます。

日本人でも日本語が難しいと思う時あるよね…
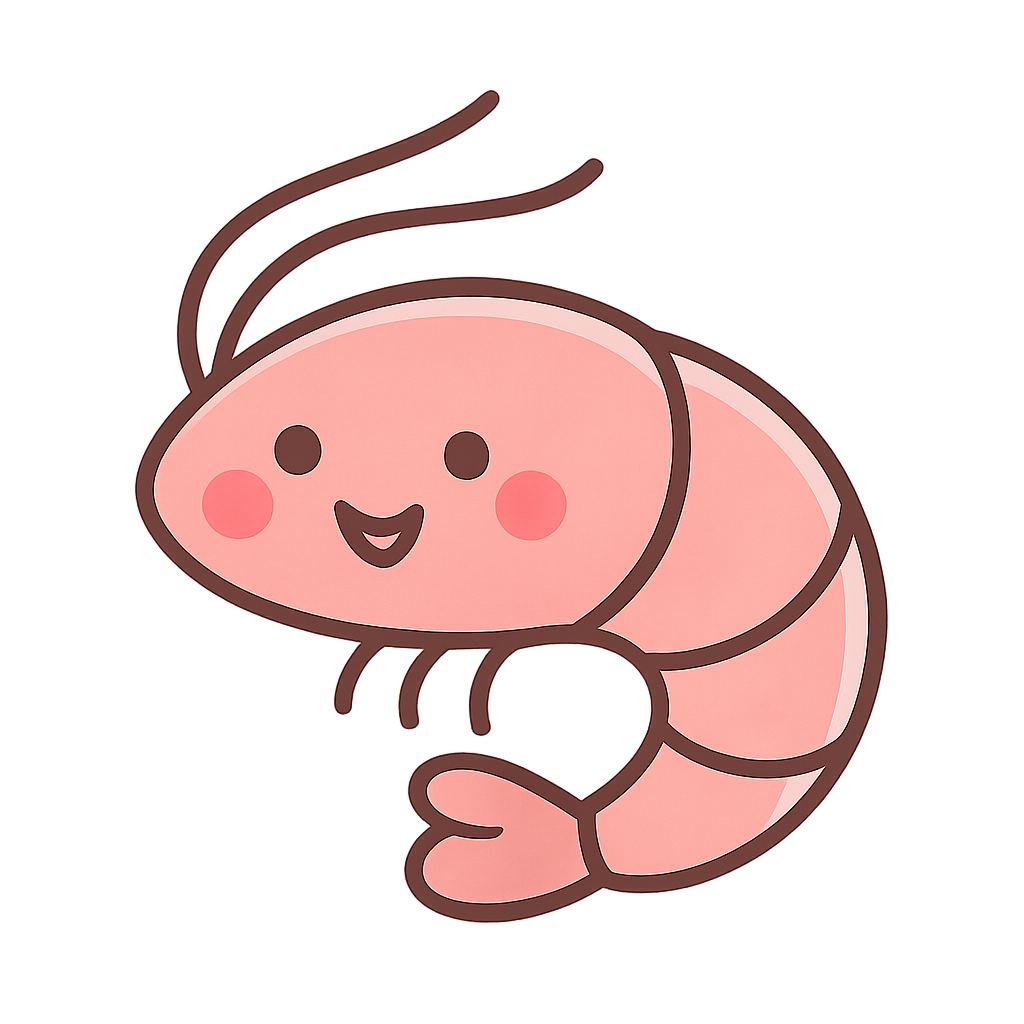
敬語なんか特にね…
1. 複雑すぎる「文字」のシステム
まず、日本語の難しさの根源として挙げられるのが、文字システムの複雑さです。
英語はアルファベットの26文字、中国語は漢字(簡体字や繁体字)、韓国語はハングルと、多くの言語が1種類の文字体系で成り立っています。一方で、日本語には、なんと4種類もの文字が存在します。
- ひらがな:46文字(「あいうえお」など)
- カタカナ:46文字(「アイウエオ」など)
- 漢字:常用漢字だけでも2,000字以上
- ローマ字:アルファベット(「Tokyo」など)
この4つの文字を、文脈や用途に応じて使い分ける必要があります。
例えば、
- ひらがなは、日本語の基本的な音を表し、助詞や助動詞、送り仮名などに使われます。
- カタカナは、主に外国語の固有名詞や外来語、擬音語・擬態語などに使われます。
- 漢字は、単語の意味を表す表意文字であり、多くの情報量を少ない文字数で伝える役割を担います。
この使い分けが、外国人にとっては最初の大きなハードルとなります。
英語と日本語の文字の比較
英語は「表音文字」であり、文字が音を表しています。たとえば “cat” という単語は、「キャ」と「ッ」と「ト」という3つの音の組み合わせで成り立っていることがわかります。
これに対し、日本語の漢字は「表意文字」であり、文字そのものが意味を持っています。たとえば、「猫」という1文字だけで「ねこ」という読みと、動物の「ねこ」という意味が込められています。
この違いは、学習の仕方に大きな影響を与えます。英語は26文字を覚えれば、あとは単語のスペルをひたすら覚えることになりますが、日本語の場合、ひらがな・カタカナを覚えた後も、果てしない数の漢字を一つ一つ覚えていく必要があります。
さらに、漢字には複数の読み方(音読み・訓読み)があり、文脈によって読み方が変わることもあります。
- 「日」:
- 音読み:「にち」「じつ」(例:毎日、日本)
- 訓読み:「ひ」「か」(例:今日、昨日)
中には、「明日(あす/あした)」のように、特殊な読み方をするものもあります。これらの複雑なルールを理解し、使いこなすことは、ネイティブの私たちでさえも難しいと感じることがあるのです。
2. 語順と主語の「曖昧さ」
日本語と英語では、文の構造が根本的に異なります。この違いも、外国人学習者にとって混乱の元となります。
- 日本語: 主語(S)+目的語(O)+動詞(V)
- 英語: 主語(S)+動詞(V)+目的語(O)
| 日本語 | 私は(S) | ラーメンを(O) | 食べる(V) |
| 英語 | I(S) | eat(V) | ramen(O) |
語順が真逆であることに加え、日本語には「主語の省略」という、世界的に見ても珍しい特徴があります。
例えば、「ご飯を食べた」という文は、主語がなくても意味が通じます。文脈から「私が」「彼が」などと推測できるからです。しかし、英語では主語を省略することは基本的にありません。
- 日本語:「明日、映画を観に行かない?」
- 英語:「Don’t you want to go to the movie tomorrow?」
この例では、「あなた」という主語が日本語では省略されています。
英語を母国語とする人にとって、誰が何をしようとしているのか、文脈から常に推測しなければならない日本語は、非常にまどろっこしく、難しく感じられるのです。
3. 日本語の「察する」文化が生む表現の難しさ
日本語の難しさは、文法や文字だけでなく、日本文化に深く根ざしたコミュニケーションのスタイルにも起因しています。それが「空気を読む」「察する」という文化です。
日本語の会話では、直接的な表現を避け、曖昧な言葉で相手に意図を伝えることがよくあります。
例えば、誘いを断る時。
- 直接的な英語:「I can’t go. I’m busy tomorrow.」(行けません。明日は忙しいので)
- 曖昧な日本語:「明日はちょっと、用事がありまして…」
この日本語の表現は、「行けない」という結論をはっきりと述べていません。しかし、日本人の間ではこれで十分に意味が伝わります。これは、相手に不快な思いをさせないための配慮でもありますが、外国人にとっては「結局、行けるの?行けないの?」と混乱を招く原因になります。
また、日本語には二重否定や受身形など、遠回しな表現が多く存在します。
- 二重否定:「彼が来ないわけではない」
- (=来る可能性がある)
- 受身形:「上司に注意された」
- (=上司が私に注意した)
このような表現は、言葉の裏にあるニュアンスを理解する必要があるため、言葉の表面的な意味だけを学んでいる外国人にとって、真意を読み解くのが非常に難しいのです。
4. 敬語という「階層」システム
日本語学習者にとって、最大かつ最も複雑な壁が「敬語」です。
日本語の敬語は、相手との関係性や社会的地位に応じて、言葉の形を変化させる非常に独特なシステムです。大きく分けて、以下の3つに分類されます。
- 尊敬語: 相手の行為や状態を高める表現(例:「見る」→「ご覧になる」)
- 謙譲語: 自分の行為や状態をへりくだる表現(例:「行く」→「参る」)
- 丁寧語: 丁寧な言葉遣いで、相手への敬意を示す表現(例:「食べる」→「食べます」)
この敬語のシステムを使いこなすには、単語や文法を覚えるだけでなく、「ウチ(身内)とソト(他人)」という日本の人間関係の概念を理解しなければなりません。
例えば、自分の会社の上司のことを、社外の人に話す時。
- 「山田部長は本日お休みです」(間違い)
- 上司(身内)に尊敬語を使っているため、相手(社外の人)に対して失礼になる
- 「山田は本日、席を外しております」(正しい)
- 上司を呼び捨てにすることで、身内であることを示し、相手(社外の人)に敬意を払う
この「敬語の方向性」を理解することは、多くの外国人にとって非常に難しいことです。欧米の言語には、これほど複雑な上下関係を示す文法が存在しないため、文化的な背景から学ぶ必要があります。
さらに、私たち日本人でさえ、敬語を正しく使えているか自信がない時があります。就職活動やビジネスシーンで敬語を学ぶ機会があることからも、その難しさが伺えます。
5. 無数の「音」と「意味」の壁
日本語には、多くの同音異義語が存在することも、難しさの一つです。
- 「はし」:
- 箸(ものを食べる道具)
- 橋(川にかかるもの)
- 端(ものの先端)
これらの単語は、発音は同じですが、意味はまったく異なります。文脈やアクセント、そして文字(漢字)を見て初めて意味を理解できます。文字システムで触れた「表意文字」としての漢字が、この混乱を解消する役割を果たしています。
英語にも同音異義語はありますが、日本語ほど多くはありません。また、日本語特有の「オノマトペ(擬音語・擬態語)」の豊富さも、外国人にとっては壁となります。
- 「ザーザー」(雨が激しく降る様子)
- 「つるつる」(肌や表面が滑らかな様子)
- 「ふらふら」(体が不安定な様子)
オノマトペは、日本語の会話や文章を豊かにする重要な要素ですが、そのニュアンスを完全に理解し、適切に使いこなすのは非常に困難です。同じ「笑う」という行為でも、「ゲラゲラ」「くすくす」「にやにや」など、多くの表現があり、その違いを学ぶには多くの時間と経験が必要です。
まとめ|日本語が「難しい」と言われる理由
あらためて、日本語が外国人にとって難しいと言われる理由をまとめてみましょう。
| 難しさのポイント | 理由の詳細 | 英語との比較 |
| 文字 | 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字の4種類を使い分ける必要がある。常用漢字だけでも2,000字以上あり、読み方も複数ある。 | 英語はアルファベット26文字の表音文字。日本語の漢字は表意文字であり、文字そのものが意味を持つ。 |
| 文法 | 主語が省略されることが多く、文脈を読み取る必要がある。語順も英語と真逆。 | 英語は基本的に主語を省略せず、SVOの語順が基本。 |
| 表現 | 曖昧な表現や遠回しな言い方が多く、真意を汲み取るのが難しい。 | 英語は直接的で、結論を先に述べる表現が一般的。 |
| 敬語 | 尊敬語・謙譲語・丁寧語を、相手との関係性や社会的地位に応じて使い分ける必要がある。「ウチとソト」の概念を理解する必要がある。 | 多くの言語には、日本語ほど複雑な上下関係を示す文法が存在しない。 |
| 単語 | 同音異義語が多く、漢字を見なければ意味が理解できないことがある。オノマトペが非常に豊富で、ニュアンスを掴むのが難しい。 | 同音異義語や擬音語・擬態語は存在するが、日本語ほどではない。 |
私たちが無意識に使っている日本語には、文字、文法、表現、文化など、実に多くの要素が絡み合っています。これらの要素が、日本語を非常に奥深く、そして同時に、世界中の学習者にとって大きな壁にしているのです。
このブログを読んで、外国人の方々が日本語を学ぶことの大変さに少しでも思いを馳せていただけたら嬉しいです。そして、これから日本語を学ぼうとしている方には、この難しさが、日本語をマスターした時の達成感をより大きなものにしてくれることを伝えたいです。

日本語は難しい!けど英語もよく分からない!
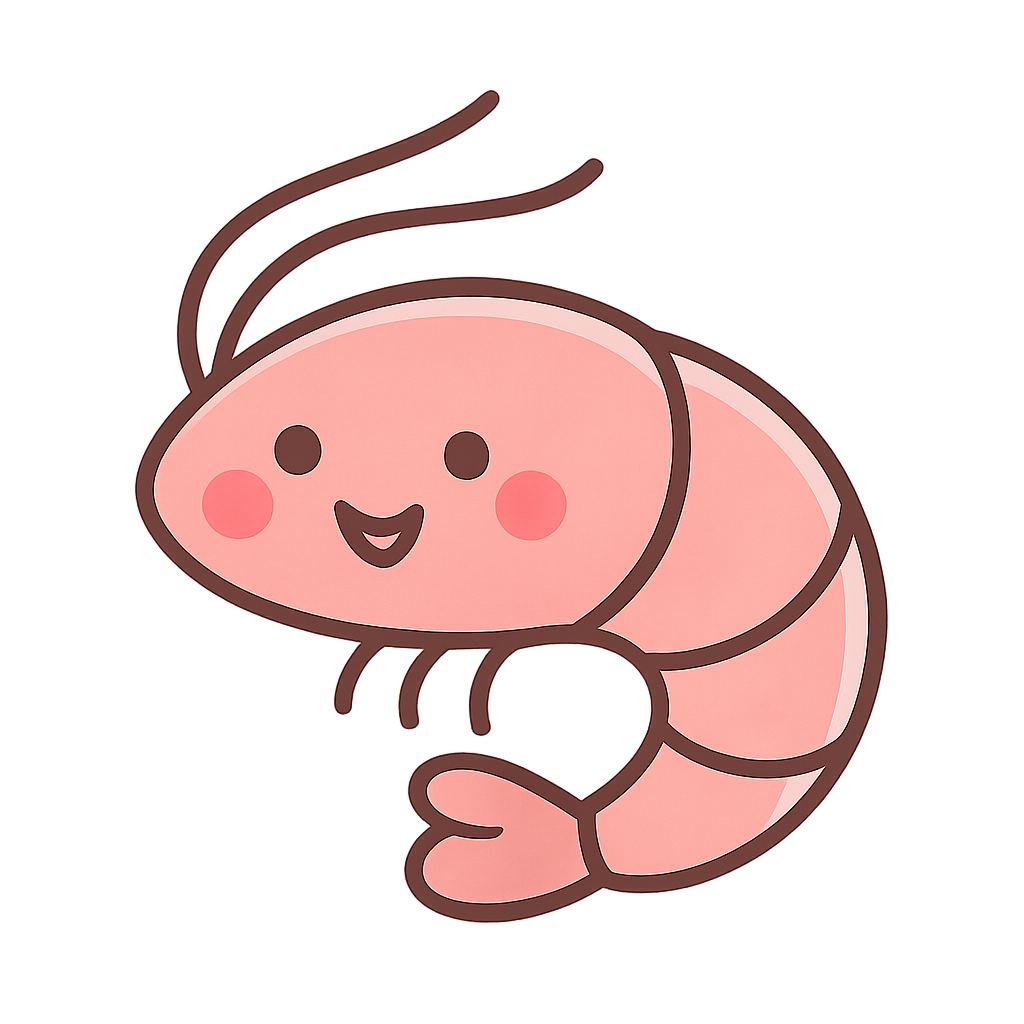
普段から学習する姿勢が大事だね

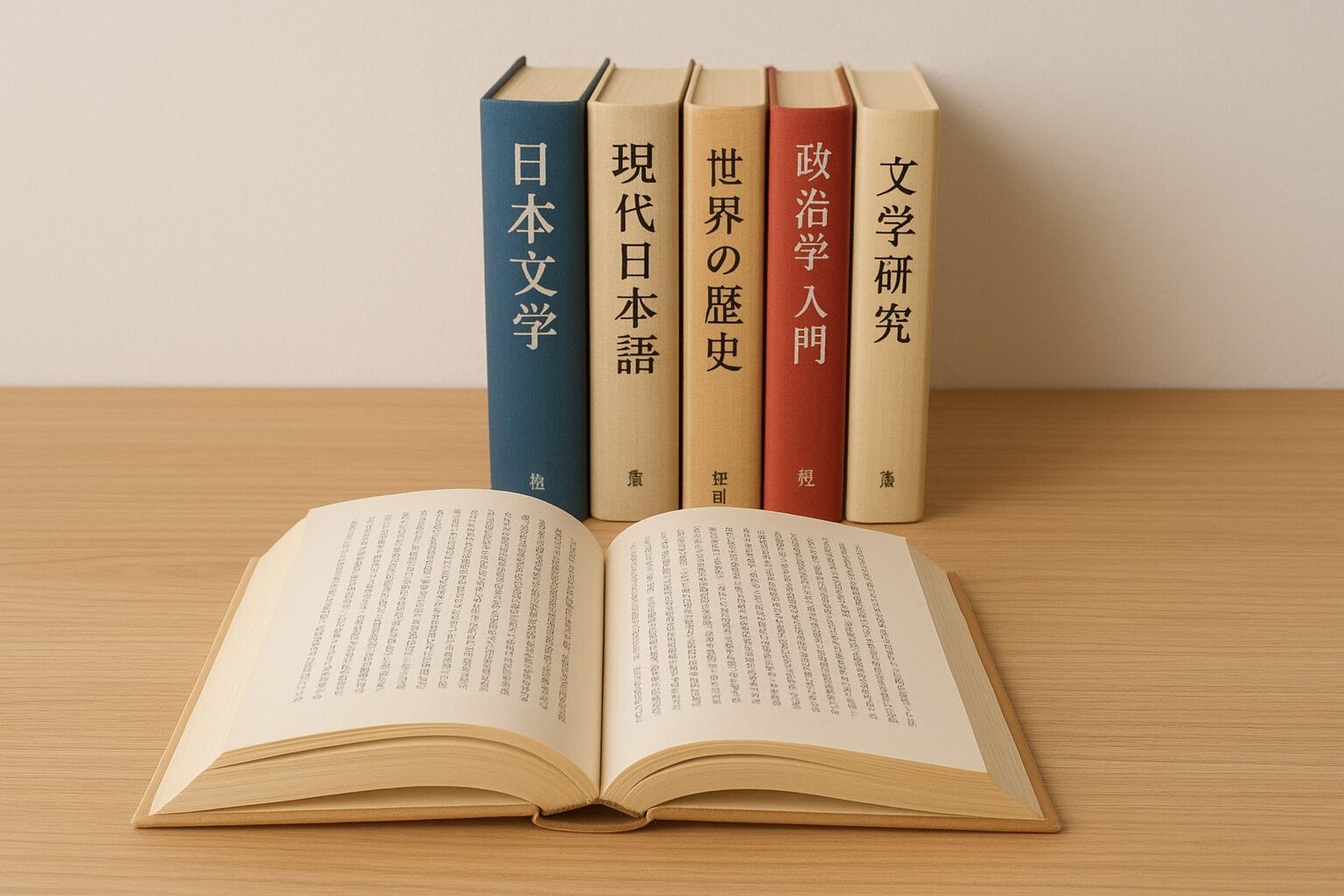


コメント