近年、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、日本中で空前のキャンプブームが巻き起こりました。しかし、2025年を迎えた今、「キャンプブームは終わった」「流行は下火になった」という声が聞かれるようになっています。果たして、この言説は本当なのでしょうか。
本レポートでは、表面的な情報に惑わされることなく、一般社団法人日本オートキャンプ協会(JAC)の公式発表である「オートキャンプ白書2024」をはじめとする信頼性の高い調査データや市場の動向を多角的に分析し、「ブーム」の終焉が意味するもの、そして日本のキャンプ市場が現在どのような段階にあるのかを深く掘り下げていきます。
結論から述べると、一時的な「ブーム」は落ち着きましたが、それは「終焉」や「衰退」ではなく、より成熟した「文化」への移行期であると分析されます。本稿では、その根拠をデータに基づき詳細に解説します。

ブームの時は行きたいキャンプ場の予約が取れなくて…
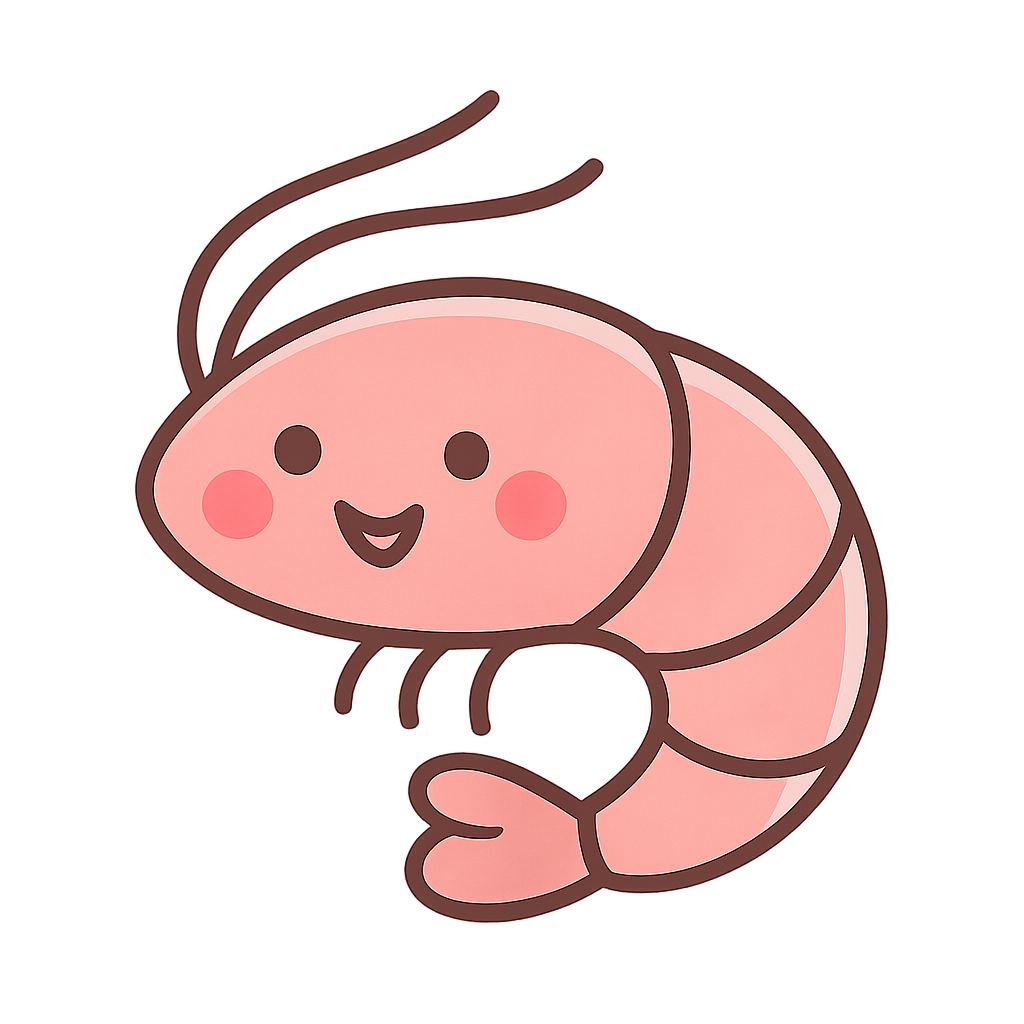
今なら予約も取れるかも!?
キャンプ人口と活動実態の変遷:量から質への転換点
まず、キャンプ人口の推移と活動実態から、市場の構造変化を紐解きます。
コロナ禍がもたらした人口の急増と現状
日本オートキャンプ協会の発表によると、2023年のオートキャンプ参加人口は600万人となり、前年比で7.7%の減少を記録しました。この数字をもって、「キャンプブームが終了した」と結論付ける報道が一部で見られます。しかし、これは市場全体を理解するための断片的な情報に過ぎません。
この人口減少は、コロナ禍において初めてキャンプを体験した「ライトユーザー」層の自然な離脱と捉えるのが妥当です。彼らは「キャンプは虫がいる」「荷物が多くて大変」「天候に左右される」といった、アウトドア活動に内在する不便さや制約を理由に、ブームが去るとともにキャンプから離れていきました。
したがって、この人口減少は市場の急拡大が収束した後の、いわば「健全な調整局面」であり、市場の長期的な安定化に不可欠なプロセスであると分析できます。
活動実態の変化:非日常から日常へ
キャンプ人口が減少した一方で、非常に興味深いデータが明らかになっています。それは、コアユーザーの活動頻度が高まっているという事実です。
2023年の年間平均キャンプ回数は5.5回と、過去最多を記録しました。これは、1年間におよそ2カ月に一度はキャンプ場を訪れている計算になります。さらに、同じキャンプ場を繰り返し訪れるリピート回数も過去最高の4.7回に達しています。
この二つのデータを総合すると、人口は減少しているものの、残った人々はより頻繁に、そして継続的にキャンプを楽しんでいることがわかります。この状況は、キャンプが「特別なイベント」や「一過性の流行」ではなく、週末や平日の「日常の延長」として人々の生活に深く根付いたことを示しています。
以下に、日本のオートキャンプにおける主要指標の推移をまとめた表を提示します。
表1:日本のオートキャンプ主要指標の推移(2022年〜2023年)
| データ項目 | 2022年 | 2023年 | 傾向 |
| オートキャンプ参加人口 | 650万人 | 600万人 | ↓ |
| 年間平均キャンプ回数 | 5.4回 | 5.5回 | ↑ |
| ソロキャンプ人口比率 | 16.6% | 19.4% | ↑ |
| キャンプ場の平均稼働率 | 20.0%超 | 19.6% | 依然高水準 |
参考資料:日本オートキャンプ協会「オートキャンプ白書2023・2024」、各種メディア記事より作成
多様化するキャンプスタイル:ソロ・デュオキャンプの隆盛

活動実態の変化は、キャンプスタイルの多様化にも現れています。
特に注目すべきは、「ソロキャンプ」の成長です。2023年、同行者の割合において「1人(ソロキャンプ)」が19.4%と過去最高の割合を占め、これまで3位だった「他の家族と」を上回り、主要なキャンプスタイルとして定着しました。ソロキャンパーは、賑やかな週末を避けてゆっくりと過ごせる「平日」にキャンプ場を訪れる傾向があるため、キャンプ場の稼働率を押し上げる重要な要因となっています。
さらに、カップルや友人同士で行う「デュオキャンプ」や、日帰りで公園などで手軽に楽しむ「パークキャンプ」といった新しいスタイルも需要を伸ばしており、キャンプ市場が単一のスタイルに依存するのではなく、多様なニーズに応える形で進化していることがわかります。
キャンプ用品市場の動向:成熟期への移行と健全な市場調整
キャンプ人口の減少が、用品市場にどのような影響を与えているかを見ていきます。
市場規模の縮小:特需の反動と在庫調整の真相
2023年の国内キャンプ用品市場規模は803億円と、前年比で15.3%縮小し、この10年で最大の落ち込み幅となりました。また、年間購入金額も8年ぶりにマイナスに転じています。この市場の縮小を象徴する出来事として、大手アウトドアメーカーであるスノーピークが、2024年2月に純利益が前期比99.9%減となった決算を発表したことは、業界内外に大きな衝撃を与えました。
しかし、これらの市場の調整局面は、長期的な崩壊を示すものではありません。業界関係者の見解によれば、これらの現象は、コロナ禍による「巣ごもり需要」という一時的な特需の反動であり、過剰に膨れ上がった小売店やメーカーの在庫を調整する動きが主な原因です。
コアユーザーが支える市場:製品トレンドの変化
市場全体が縮小傾向にあるにもかかわらず、一部のカテゴリでは安定した需要が見られます。主力であるテントの輸入金額は、2023年に前年を大きく下回ったものの、長期的な視点で見るとコロナ禍以前の2019年と比較して右肩上がりの傾向が続いています。
このデータは、市場が「安価なエントリーモデル」を求める新規ユーザー層から、「より高機能で長く使える本質的なギア」を求める経験豊富なコアユーザー層へと需要の中心がシフトしていることを示唆しています。
このトレンドを裏付けるように、2024年のキャンプギア賞では、軽量かつ高機能なソロ・デュオ向けのテントが最優秀賞に輝き、焚き火台部門でも機能性やデザイン性に優れた製品が評価されています。これは、ライトユーザーの離脱後も、キャンプを継続する人々が、自身のスタイルに合った、より質の高い製品を求めていることを物語っています。
グローバル市場との比較
国内市場が調整局面にある一方で、世界のキャンプ機器市場は、2025年の967億5,000万米ドルから2032年には1,722億1,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率(CAGR)は8.58%と見込まれています。
このことから、日本のキャンプ市場の動向は、グローバル市場全体の成長トレンドとは独立した、独自の成熟段階に入ったと分析できます。国内市場の成長の鍵は、新規参入者を開拓することだけでなく、定着したコアユーザーの多様なニーズに応える製品・サービスの提供にあると言えるでしょう。
キャンプ場の現状と課題:淘汰ではなく、再編の時代へ
最後に、キャンプ場の運営状況に焦点を当て、ユーザーが抱く「キャンプ場は閉店しているのか?」という疑問に答えます。
「キャンプ場閉鎖」の真実
一部でキャンプ場の閉鎖が報じられていることは事実ですが、そのほとんどは需要の減少による経営破綻ではありません。資料を分析すると、閉鎖の理由は「改修工事」や「天災」といった特定の個別事情によるものであることが明らかになっています。
例えば、アメリカの国立公園内のキャンプ場が2024年、2025年に閉鎖されるというニュースは、水道管の改修工事が理由です。また、富山県で発生したキャンプ場の閉鎖は、ツキノワグマによる被害が原因でした。
これらの事例は、需要の減少による全国的な閉鎖の連鎖を示唆するものではなく、それぞれのキャンプ場が直面する固有の課題に対応した結果であり、市場全体の傾向とは切り離して考えるべきです。
稼働率と利用料金:安定した運営状況
キャンプ場への需要は依然として安定しています。2023年のキャンプ場の平均稼働率は19.6%と、前年比でわずかに下回ったものの、依然として非常に高い水準を維持しています 2。
また、キャンプ場の平均利用料金は、大人2人、子供2人の1区画あたりで初めて5,000円を超え、5,041円となりました。この料金上昇の背景には、人件費や電気代をはじめとする運営コストの増大があります。このコスト増に対応するため、キャンプ場の47.9%がシーズン料金を採用しており、これもまた、需要が依然として旺盛であり、運営側が価格転嫁を可能としている証拠と言えるでしょう。
新たな課題とチャンス
日本のキャンプ場業界は、需要が安定している一方で、構造的な課題も抱えています。特に深刻なのが、経営者の高齢化に伴う後継者不足です。今後、この問題が原因で小規模なキャンプ場が休廃業に至る可能性は否定できません。
しかし、この課題は新たなビジネスチャンスを生み出しています。高齢化や後継者不足で放置された「耕作放棄地」を、地域の活性化と両立させながらキャンプ場として再生させる成功事例も生まれており、業界が課題解決とイノベーションを同時に進めていることがわかります。また、キャンピングカー市場も2024年に過去最高の売上を記録するなど、新しい宿泊体験への需要が高まっており、キャンプ業界全体が再編と進化の時代を迎えています。
結論:ブームが終わり、キャンプは「文化」となった
これまでの分析を総括すると、2025年現在、「キャンプブームは終わった」という言説は、市場の真の姿を捉えていません。データが示すのは、一過性の流行が終息し、健全な市場調整を経て、キャンプがより成熟した段階へと移行しているという事実です。
「ブームの終焉」がもたらすポジティブな側面
ライトユーザーの離脱は、業界にとっていくつかのポジティブな側面をもたらしています。
まず、キャンプの経験が浅い人々が離れたことで、キャンプ場での迷惑行為が減少する傾向にあると期待されています。ゴミの放置や深夜の騒音といった問題が減ることで、キャンプ本来の「自然の中で静かに過ごす」という楽しみが回復しつつあります。
また、ブーム時には予約が困難だった人気キャンプ場でも、状況が改善されつつあり、コアユーザーにとっては以前よりも落ち着いた環境でキャンプを楽しめるようになっています。
以下に、キャンプから離れていった人々が挙げた主な理由をまとめます。
表2:キャンプをやめた主な理由ランキング
| 順位 | 理由 |
| 1位 | 寒い、暑い、台風などの自然現象 |
| 2位 | 荷物が多い |
| 3位 | 虫がいる |
参考資料:SNS調査、アンケート調査より作成
この表は、ライトユーザーが離脱した理由が、キャンプの本質的な不便さにあることを明確に示しています。ブームの終焉は、その不便さを受け入れ、それでもキャンプを愛する人々だけが残る「健全なふるい分け」であったと言えるでしょう。

最近だとマダニの感染症も怖いよね…
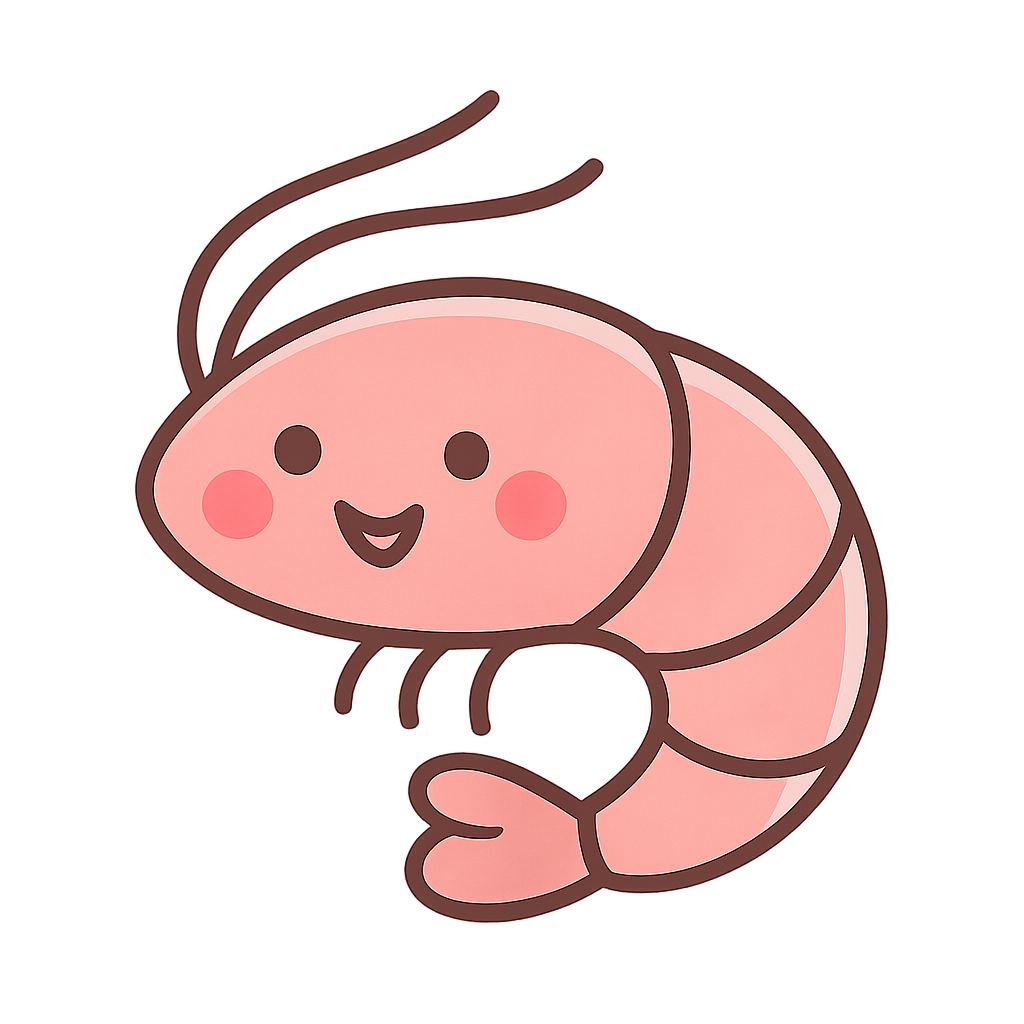
マダニはねぇ…
最終的な展望:成熟したキャンプカルチャーの未来
日本のキャンプ市場は、もはや万人受けする安価な商品やサービスが大量に消費される段階にはありません。今後は、ファミリー層、ソロキャンパー、デュオキャンパーなど、それぞれの特定層の深いニーズに応える、専門的で質の高い製品やサービスが主流になっていくと予測されます。
キャンプは、一過性の流行として消費される時代を終え、「日常の延長」として国民の生活に深く根ざした「文化」へと変貌を遂げました。この新たなステージは、日本のキャンプカルチャーがより深く、豊かに、そして持続的に発展していくための確固たる基盤となるでしょう。

マダニはちょっとコワイけど、草むらとかに気をつけてキャンプを楽しみたいね
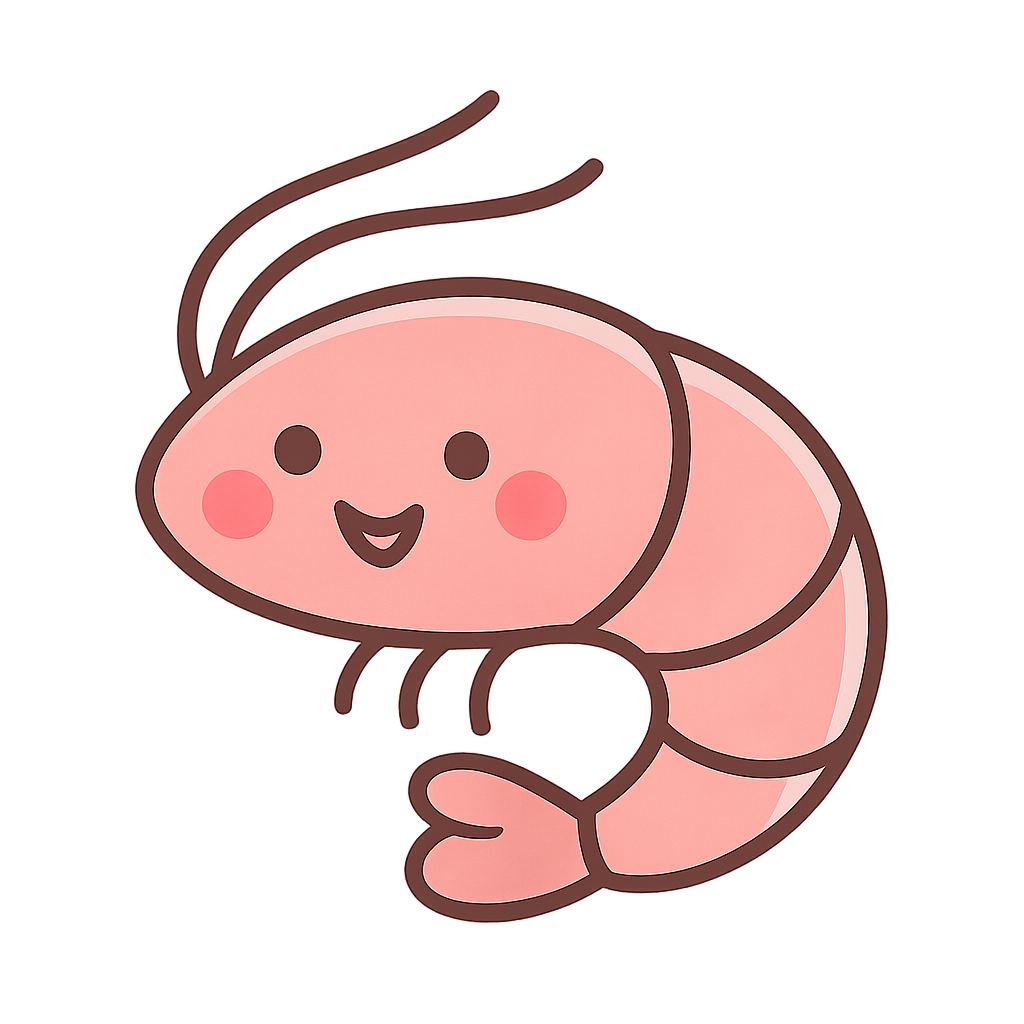
虫除けスプレーは必須だね




コメント