湖面は、夜明けを待つように静かに揺れていた。
濃い群青の水に、かすかな光が差し込み、世界はひととき青の深みに包まれている。
湖畔のベンチに、白髪交じりの博士と、細い万年筆を胸ポケットに差した詩人が並んで腰を下ろしていた。
「人が青に惹かれるのはなぜか。君はどう思う?」
博士は湖に目をやったまま、静かに問いかけた。
詩人は微笑んで、靴先で小石を転がした。
「青は、遠くを呼ぶ色だよ。空は限りなく高く、海は底知れず深い。
私たちが青に惹かれるのは、未知への憧れを映しているからだ。」
博士は首を振る。
「それは詩的解釈だな。だが、科学的にはもっと単純だ。
人類は進化の過程で空と海を常に目にしてきた。
青い光を捉える短波長受容体は、生き延びるために必要だった。
つまり、青は安心と秩序を象徴する色なんだ。」
「安心と秩序……か」
詩人は湖を覗き込み、指先で水面を揺らす。
「だが博士、その説明では足りない。
どうしてこの胸の奥が、こんなにも締めつけられるように震えるんだ?」
博士は言葉を失った。
湖面は波紋を広げ、その一枚一枚が空の青を映し返す。
科学では測れない震えが、確かにそこにあった。
「……なるほど。人は青に、理屈を超えた何かを託しているのかもしれんな。」
博士は眼鏡を外し、静かに微笑んだ。
詩人は空を仰いだ。
夜明けの一筋の光が湖を照らし、青はやがて淡い金色に変わっていった。
「ほら、博士。青は消えゆくからこそ、美しいんだ。」

夜明けの光が湖を染めると、青は徐々に退き、黄金色が広がっていった。
博士と詩人は並んでその光景を眺めていた。
博士が静かに言った。
「確かに、青は消えゆくから美しいのかもしれない。
だが、それでも私は思うのだよ。
青とは、世界が人間に与えた“信号”だ。
安心せよ、ここに水がある、ここに空がある――そう告げる、生存のための色だと。」
詩人は首を振り、微笑んだ。
「いいや博士。青はただの信号じゃない。
私たちが青に惹かれるのは、そこに“未来”を見ているからだ。
はるか遠い空の果て、深い海の底。
届かない場所へ、心だけが自由に旅をする……それが青なんだよ。」
博士は目を細めた。
「安心と未来か。なるほど、君と私の青はずいぶん違うな。」
詩人は立ち上がり、湖へ視線を投げる。
「違うようで、同じかもしれない。
だって博士、安心できるからこそ人は未来を夢見られるんだ。
そして未来を夢見るからこそ、安心を求める。」
博士はしばし黙り込み、それから笑みを浮かべた。
「……結局、青の正体は“人の心”そのものなのかもしれんな。」
湖面に映る空は、淡い青を残しつつ、ゆっくりと朝へと溶けていった。
博士と詩人の影もまた、その光の中に溶け込んでいった。
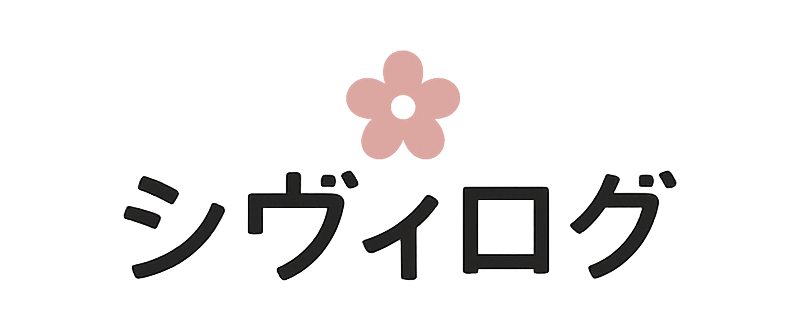



コメント