はじめに:なぜ今、マダニとSFTSが注目されるのか?
近年、マダニを介して感染する「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」という感染症が、日本国内で報告されるケースが増加しています。ニュースやSNSでも「マダニに注意」「SFTSに感染」といった情報がたびたび話題となり、不安を覚えている方も多いのではないでしょうか。
SFTSは、発熱や血小板・白血球の減少を主症状とし、重症化すると多臓器不全を引き起こすこともある、非常に危険な病気です。致死率は高く、国内でも多くの死亡例が報告されています。この病気を引き起こすSFTSウイルスは、マダニに咬まれることで人や動物に感染します。
しかし、なぜこのウイルスは日本に現れたのでしょうか?マダニは昔から日本に生息していましたが、SFTSウイルスによる感染症が報告されるようになったのは比較的最近のことです。このウイルスの起源、そして日本における感染拡大の背景には、一体何があるのでしょうか。
この記事では、Webライターである私が、公的なデータや研究論文に基づき、SFTSの謎に迫ります。SFTSウイルスはどこからやってきたのか、日本での感染動向はどのように推移しているのか、そして私たちにできる対策は何か。データと科学的な視点から、その実態を明らかにしていきます。
第1章:SFTSとは何か?その正体と感染経路
SFTSについて深く掘り下げる前に、まずはこの病気の基本的な知識を確認しておきましょう。
SFTSの概要と症状
SFTSは、SFTSウイルスによって引き起こされるウイルス性疾患です。潜伏期間は通常6日から14日程度で、主な症状は以下の通りです。
- 発熱(38℃以上)
- 消化器症状(食欲不振、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢など)
- 全身倦怠感、筋肉痛
- 意識障害、けいれん、出血傾向
特筆すべきは、血液検査で白血球と血小板の著しい減少が認められる点です。重症化すると、DIC(播種性血管内凝固症候群)や多臓器不全を引き起こし、死に至ることもあります。現在のところ、SFTSに対する特異的な治療法やワクチンは確立されていません。そのため、対症療法が中心となり、早期の診断と適切な治療が予後を左右します。
SFTSウイルスの感染経路
SFTSウイルスは、主にマダニを介して人や動物に感染します。特に、国内でSFTSウイルスの保有が確認されているマダニ種として、フタトゲチマダニやタカサゴキララマダニなどが挙げられます。これらのマダニが、ウイルスを保有した状態で人や動物を吸血することで感染が成立します。
また、ごく稀なケースではありますが、SFTSを発症した動物(主にイヌやネコ)から人へ、または人から人へ、血液や体液を介して感染した事例も報告されています。しかし、大多数の感染はマダニの咬傷によるものであるため、マダニ対策が最も重要となります。
SFTSウイルスはどこからやってきたのか?その起源を探る
SFTSは比較的新しい感染症ですが、その起源は一体どこにあるのでしょうか。この問いに答えるためには、ウイルスの系統樹解析や、感染症の発生動向に関する国際的なデータに目を向ける必要があります。
中国で初めて報告されたSFTS
SFTSウイルスによる感染症が初めて公式に報告されたのは、2009年の中国です。中国の湖北省、河南省、山東省などで、原因不明の出血熱患者が多発しました。当初は既知のウイルス性出血熱との関連が疑われましたが、研究の結果、これまでに報告例のない新しいウイルスが患者から分離・同定されました。これがSFTSウイルスです。
中国の研究者たちは、このウイルスがブニヤウイルス科フレボウイルス属に属する新しいウイルスであることを突き止め、2011年にその存在を医学誌『ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン』で発表しました。この論文が、世界中でSFTSの存在を広く知らしめるきっかけとなりました。
ウイルスの系統解析から見えてくる「東アジア起源説」
SFTSウイルスの起源をさらに詳しく調べるため、科学者たちはウイルスの遺伝子配列を解析し、系統樹を作成しました。系統樹とは、ウイルスの進化の道筋を図示したもので、遺伝的に近いウイルスほど枝が近くに位置します。
日本で確認されたSFTSウイルスの遺伝子配列は、中国や韓国で確認されたウイルスと非常に高い相同性(似ている度合い)を示しています。特に、中国のウイルスとの類似性が高く、SFTSウイルスは中国中部から東部にかけての地域で発生し、その後、人や動物の移動、あるいはマダニの分布拡大に伴って、東アジア地域に広がった可能性が高いと考えられています。
これは、日本で初めてSFTS患者が確認された2013年よりも前に、韓国でもSFTS患者が報告されていることとも一致します。SFTSは、まさに東アジア地域固有の感染症として、その脅威を広げてきたのです。
日本のSFTS感染動向:データで見る「現状」
SFTSの起源が東アジアにあることがわかったところで、次に日本の感染動向を見ていきましょう。厚生労働省や国立感染症研究所が公表しているデータを基に、日本におけるSFTSの広がりを追跡します。
2013年の初報告から急増する患者数
日本で初めてSFTS患者が確認されたのは2013年1月です。その後、患者数は年々増加傾向にあります。
国立感染症研究所のデータによると、年間のSFTS確定診断例は、
- 2013年:28例
- 2014年:53例
- 2015年:60例
- 2016年:66例
- 2017年:94例
- 2018年:101例
- 2019年:114例
- 2020年:107例
- 2021年:119例
- 2022年:121例
(※データは年によって変動する可能性あり。最新のデータは国立感染症研究所の公式発表を参照してください)
このように、2013年の初報告からわずか数年で、年間100例を超える患者が報告されるようになりました。この急増は、SFTSが日本国内で定着し、脅威が拡大していることを示唆しています。
SFTS患者の地理的分布:西日本に集中する傾向
SFTSの患者は、日本全国で報告されていますが、その分布には明確な特徴があります。データを見ると、西日本に患者が集中していることがわかります。
具体的には、山口県、広島県、愛媛県、高知県、宮崎県、鹿児島県などの地域で多くの患者が報告されています。これは、これらの地域が、SFTSウイルスを媒介するマダニの生息に適した気候や植生を持っているためと考えられます。
SFTSウイルスは、イヌやネコ、シカ、イノシシなどの野生動物が保有していることがわかっています。これらの動物は、マダニの主要な吸血源です。そのため、野生動物との接触機会が多い地域や、マダニが生息しやすい草木が茂る地域では、SFTSに感染するリスクが高まるのです。
死亡率の高さ:データの裏にある重い現実
SFTSの致死率は、報告されているデータから見ても決して低くありません。日本のSFTS患者の致死率は、約20〜30%とされています。これは、デング熱やウエストナイル熱といった他のウイルス性疾患と比べても高い数値です。
特に高齢者や基礎疾患を持つ人が重症化しやすい傾向にあり、SFTSは単なる「ダニによる感染症」として軽視できない、深刻な公衆衛生上の課題となっています。
SFTSの脅威拡大と今後の展望
SFTSは、なぜ日本でこれほどまでに広がったのでしょうか?その背景には、複合的な要因が絡み合っていると考えられます。
気候変動とマダニの生息域拡大
マダニは、気温や湿度が高い環境を好みます。近年の地球温暖化による気温上昇は、マダニの活動期間を延長させ、生息域を北へと拡大させている可能性があります。
また、シカやイノシシといった野生動物の個体数増加も、マダニの吸血源を増やし、SFTSウイルスが広がる機会を増大させています。
野生動物と人間の生息域の重なり
都市化が進む一方で、耕作放棄地の増加や過疎化により、山間部と人間の居住域との境界線が曖昧になっています。その結果、イノシシやシカといった野生動物が里山や住宅地周辺に出没するケースが増え、人間がマダニに接触するリスクが高まっています。
知識の普及と医療体制の課題
SFTSは比較的新しい病気であるため、その認知度はまだ十分とは言えません。医療従事者の中にも、SFTSの診断経験が少ない医師がいるかもしれません。
しかし、SFTSは早期診断が非常に重要です。マダニに咬まれた自覚がある場合や、野外活動後に発熱や全身倦怠感などの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診し、マダニに咬まれた可能性を医師に伝えることが大切です。
SFTSパンデミックの可能性は?
SFTSが人から人へ感染するケースは稀であるため、COVID-19のような大規模なパンデミックを引き起こす可能性は低いと考えられています。しかし、感染者数が増加すれば、人から人への感染リスクもわずかながら高まります。
また、SFTSウイルスの変異によって、感染力が強まる可能性もゼロではありません。そのため、継続的なウイルス監視体制の構築と、一般市民への啓発活動が不可欠です。
私たちができるSFTS対策
SFTSは、正しい知識と予防策を講じることで、そのリスクを大幅に減らすことができます。
マダニに咬まれないための予防策
最も効果的なSFTS対策は、マダニに咬まれないようにすることです。
- 服装:草むらや藪に入る際は、長袖・長ズボンを着用し、肌の露出を避ける。
- 靴:サンダルは避け、足を覆う靴を履く。
- 忌避剤:マダニ用忌避剤(DEETやイカリジンなど)を、肌や衣類に塗布する。
- チェック:屋外活動後には、体や衣類にマダニが付いていないか、入念にチェックする。特に、耳の裏、脇の下、太ももの付け根、髪の毛の中などは見落としやすいので注意が必要です。
- ペット:ペットに付着したマダニが、家の中に持ち込まれることもあります。ペットのダニ予防も忘れずに行いましょう。
もしマダニに咬まれたら?
もしマダニに咬まれているのを発見しても、無理に自分で引き抜こうとしないでください。マダニの口器が皮膚の中に残り、炎症や感染を引き起こす可能性があります。
- 医療機関を受診する:すぐに皮膚科などの医療機関を受診し、医師に除去してもらいましょう。
- 症状を記録する:いつ、どこでマダニに咬まれたか、その後どのような症状が出たかなどを記録しておくと、診察時に役立ちます。
地域社会全体での取り組み
SFTSは、個人だけでなく、地域社会全体で取り組むべき課題です。
- 野生動物の管理:野生動物の生息域と人間の生活圏を分けるための取り組み。
- 草刈り:マダニの生息地となる草むらの管理。
- 情報共有:医療機関や保健所、住民が連携して、SFTSに関する情報を共有する。
まとめ:SFTSと向き合うための最終的な提言
この記事では、SFTSウイルスの起源が中国にあり、その後日本へと広がってきたこと、そしてその感染動向がデータで示されていることを解説しました。SFTSは、単なる「地方の病気」ではなく、日本全体で注意すべき深刻な公衆衛生上の脅威です。
しかし、その脅威は、正しい知識と予防策によって大きく軽減することができます。
- SFTSはマダニが媒介する、致死率の高い病気である。
- ウイルスの起源は中国にあり、東アジア全域で感染が広がっている。
- 日本では特に西日本で患者数が多く、年々増加傾向にある。
- マダニに咬まれないための予防策を徹底することが最も重要である。
- 咬まれた場合は、自分で取ろうとせず、すぐに医療機関を受診する。
私たちは、SFTSという新しい脅威を前に、不安を感じるかもしれません。しかし、その不安は、確かな知識と具体的な対策によって、行動へと変えることができます。この記事が、SFTSの脅威を正しく理解し、自らの身を守るための一助となることを願っています。
【参考文献】
- 国立感染症研究所「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」
- 厚生労働省「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に関するQ&A」
- Yu XJ, et al. (2011). Fever with Thrombocytopenia Associated with a Novel Bunyavirus in China. The New England Journal of Medicine.
- 日本感染症学会「SFTS診療の手引き」


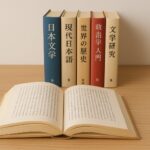

コメント